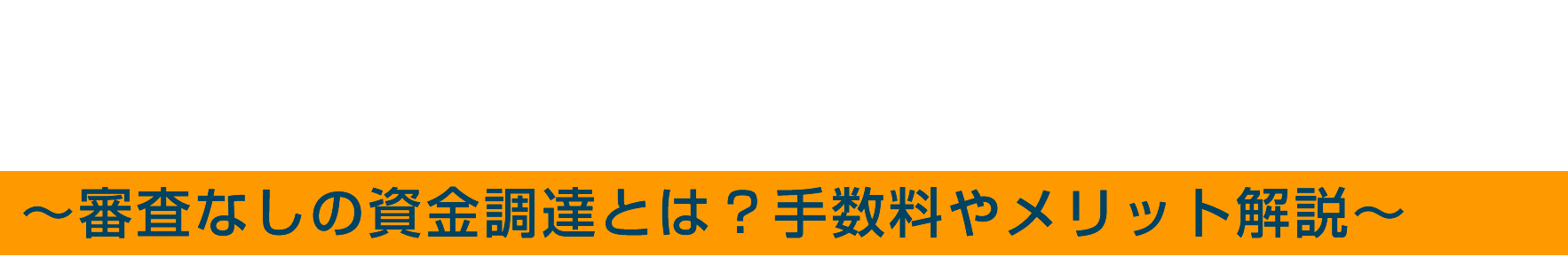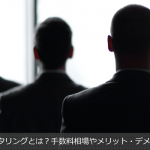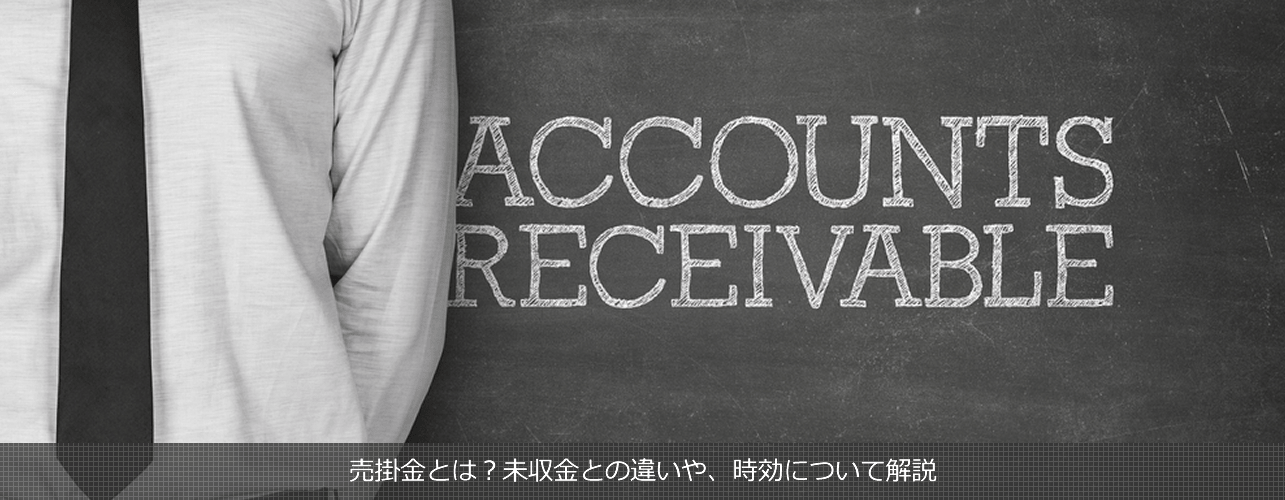
簿記の基本となる売掛金とは?
企業の取引の中でよく聞く売掛金。
なんとなく聞いたことがある人は多いと思いますが正確に答えることが出来る人は、意外と少ないのではないでしょうか。
簿記の基本となる売掛金ですが、いざ売掛金とは?と聞かれると答えに困る人は意外と多いと思います。
また、売掛金と似た未収金や売掛債権との違いについても混同してしまうことがあるので、この記事では企業取引の基本中の基本となる売掛金について詳しく説明していきます。
目次
売掛金とは?その意味から仕組みまで
この章では、簿記の基本となる売掛金について説明していきます。
売掛金の意味や売掛金の仕組み、売掛金が商取引で使われる理由について分かりやすくまとめていきます。
売掛金の意味
売掛金とは、信用取引によって商品やサービスを提供したが、その対価をまだ受け取っていない状態で代金を受け取る権利のことをいいます。
売掛金は代金の支払いが手形になっておらず、信用取引とは簡単にいうと代金の後払いのことです。
売掛金の仕組み
次に売掛金の仕組みについて説明します。
企業が商品やサービスを販売するとその対価として現金を支払います。
しかし企業は何度も取引をするので1か月分はまとめて払うことが多いのです。
1か月後にまとめて支払いますよ、という約束が売掛金の仕組みです。
商取引で売掛金が利用される理由
では、なぜ商取引で売掛金が利用されるのでしょうか。
先ほどの売掛金の仕組みのところでも触れましたが、取引の度に決済をするのは非効率だからです。
現金を用意するにも銀行に行く手間がかかりますし、両替手数料や振込も同様に手数料がかかります。
売掛金であれば決められた期間で1回まとめて精算すれば良いので効率が良いのです。実務上ではほとんどの企業間取引が掛取引で行われているほどです。
この章で、売掛金についての基本情報を紹介しました。
では次の章では、売掛金と混同しやすい、「未収金、手形、売掛債権」の違いについて詳しく説明していきます。
似ているようで違う!未収金・手形・売掛債権との違い
前章で、売掛金について説明しました。
そこで以下では、売掛金とよく間違える未収金、手形、売掛債権との違いについて説明していきます。
未収金との違い
売掛金と未収金は、お金が未回収の状態という意味ではよく似ています。
しかし、売掛金と未収金は明確に違います。
売掛金について先ほど説明しましたがおさらいの意味でもう一度説明します。
売掛金とは、商品やサービス、つまり営業取引によって発生する未回収資金のことです。
一方、未収金は、営業外取引によって発生する未回収資金のことをいいます。
営業外取引とは、固定資産の売却や会社の余剰資金で購入したマンションの賃貸収入などのことをいいます。
売掛金と未収金の明確な違いは営業活動で生じたものなのか営業外活動によって生じたのかの違いという訳です。
受取手形との違い
次に、売掛金と受取手形の違いについて説明します。
売掛金と受取手形は代金の後払いという性格は一緒です。
しかし決定的に違うのは、法的拘束力があるかないかです。
売掛金には、法的な拘束力はありません。
言い方を変えれば企業同士の信用で成り立っている口約束のようなものです。
一方受取手形には、法的な拘束力があり、専用の法律まで規定されているほどです。
手形は、手形という証券に期日や名前を記入するので、お金を受け取る者、支払う者が明確になります。
法的な拘束力が受取手形のほうが圧倒的に強いため、売掛金よりも受取手形で取引した方が、貸倒リスクが少ないので安心感は強いです。
売掛債権との違い
この章の最後に、売掛金と売掛債権との違いについてみていきましょう。
売掛債権とは、まだ受け取っていないの債権の総称を指すので、売掛金と受取手形はどちらも売掛債権です。
以上、この章では売掛金と混同しやすい「未収金、受取手形、売掛債権」の違いについて説明しました。
売掛金は、商取引上とても便利なものですが、売掛金のリスクはどのようなものがあるのでしょうか。
以下では売掛金の回収方法や時効についても説明していきたいと思います。
時効はあるの?回収方法と貸し倒れリスクの減らし方
今までのところで、売掛金の説明や売掛金と混同しやすい未収金などとの違いについて説明してきました。
この章では、売掛金の時効や回収方法、貸し倒れリスクの軽減方法についてまとめていきます。
売掛金の時効
売掛金は口約束のようなものと説明しましたが、もしも取引先が入金を忘れていた場合、いつまで売掛金として効力があるのでしょうか?
実は、売掛金の時効は、商品やサービスによって異なります。
一般的な商品の売買代金の債権の時効は2年で、宿泊費や飲食代は1年、建設業の工事費用の売掛金は3年など商品サービスによって売掛金の時効の違いがあります。
ただどのような商品サービスだとしても売掛金には時効があるので、売掛金が予定通り回収出来なかった場合は早急に動く必要があるのです。
売掛金が支払われない理由
売掛金が予定通り回収できないのには理由があります。
どのような理由で売掛金の入金が遅れてしまうのでしょうか?
単純にミスで売掛金の支払いが遅れた場合
実務上で一番多いのが、何らかの手違いによる売掛金の支払い遅れです。
単純なミスで売掛金の支払いが遅れた理由のほとんどの場合が人為的な間違い。
この場合は、取引先に連絡を入れて確認してもらうだけで、ほぼ間違いなく売掛金の回収は出来るのであまり問題ではありません。
売掛金を支払う余力がない場合
売掛金に入金が度々遅れる場合は、取引先の経営が苦しい可能性が強くあります。
将来的に、倒産の可能性があるので、売掛金が入金されないという最悪の場合も想定しなければいけません。
このケースの場合は思い切って取引を切ってしまうか、現金取引のみに切り替えたほうが良いです。
馴染みの取引先だとなかなか言いづらいとは思いますが、将来的に売掛金が焦げ付く芽は早めに絶っておきましょう。
支払う意思がない場合
このケースが一番厄介です。
資金に余力があればまだいいですがこのケースで資金に余裕があるケースはほとんどないです。
倒産や夜逃げのリスクも十分あるので、早急に売掛金の回収のために手を打つ必要があります。
売掛金の回収方法
それではここから売掛金を回収する方法を5つの手順に分けて説明していきます。
1 何はともあれ交渉をする
売掛金を回収できなかった場合にます最初にやることは、相手方との交渉です。
支払期日の延長や分割払いの提案などの柔軟な対応をしたほうが無難です。
確実に売掛金を回収するために相手の負担にならないように交渉するのがポイントです。
2 相殺できる債務を探す
取引先の買掛金があれば、売掛金と相殺して、売掛金が回収出来なかった場合の損失を軽くすることも大切です。
3 内容証明郵便で対応する
交渉や売掛金の相殺をしても埒があかない状況になってしまったら、売掛金の回収をしたい旨の内容を内容証明郵便で相手方に通知する方法が有効です。
内容証明郵便とは、郵便局が、いつ、だれが、だれ宛にどんな内容の手紙を書いたかを公的に証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便は相手方にプレッシャーを与える方法になるので有効な手段といえます。
4 債権譲渡
債権譲渡とは、売掛金を払ってくれない相手方が保有している別の会社の売掛金を譲渡してもらう方法です。
売掛金を払ってくれない相手方が支払ってくれなくても、別の会社の売掛金から回収するといった方法です。
5 裁判
以上までのことをしても売掛金が回収出来ない場合の最終手段が裁判になります。
裁判での解決は訴訟費用や弁護士を雇う費用がかかるうえに確実に売掛金を回収できるというわけでもないので最終手段という形になります。
以上が、売掛金を回収する方法でした。
やはり売掛金は受取手形と違い法的拘束力が弱いため確実に回収出来る方法がないというのが正直なところです。
では、売掛金を未回収にしない対策はないのでしょうか?
リスクを減らしたいなら事前にファクタリング利用がおすすめ
今までは、売掛金の回収方法について説明してきましたが、そもそも売掛金には性質上、未回収のリスクが付きまといます。
未回収のリスクを減らすためには、そもそも売掛金をを減らせばいいのです。
そこで売掛金の回収リスクを減らすには、事前にファクタリング利用をすることがおすすめです。
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却し、ファクタリング会社が売掛金の代行を行ってくれるサービスです。
売掛金が確実に入金されますし、何より売掛金回収の手間が省けます。社員に売掛金の回収をさせるぐらいなら、ファクタリング会社に任せてしまって、社員は本業に力を入れてほしいものです。
売掛金の回収を確実にかつ手間をかけずに行いたいのであればファクタリングの利用がおすすめです。
最後に
今回は、売掛金の意味や仕組みを説明していきました。
また売掛金と混同しやすい、未収金、受取手形、売掛債権の違いについてもまとめました。
売掛金の未回収は、実務上よくおこります。
その対策にファクタリングをご希望の方は以下の記事で紹介しておりますので、ご一読ください。